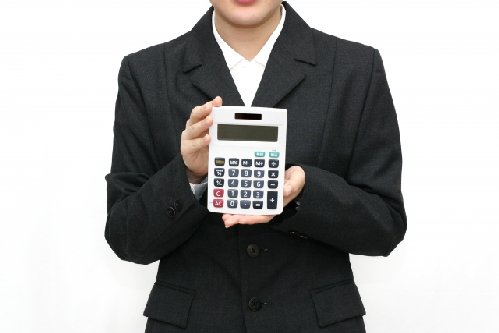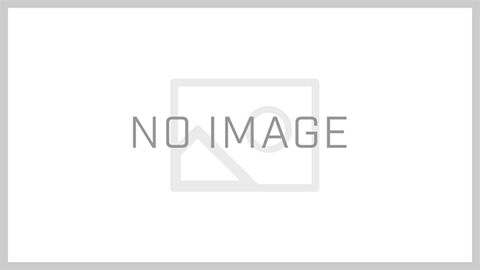借金がかさんでどうにも返済ができなく
なった時、行うのが債務整理です。
債務整理とは、読んで字のごとく
「債務を整理する」制度です。
その方法には、任意整理、特定調停、
個人再生、自己破産と4種あります。
いずれも借金は減免されますが、デメ
リットもあり、自己破産では職業や資格
の取得が一定期間制限されることもあります。
債務整理の際に、弁護士や認定司法書士
が債務者からの依頼を引き受けた時に、
債権者に送る通知が、「受任通知」というものです。
この受任通知は、単に「引き受けました」
というだけの挨拶状ではなく、
法的な効力もあるのです。
そこで今回は、その受任通知の効力や、
督促が停まる理由などを紹介していきます!
債務整理での受任通知とは?

借金の取り立て(督促)は辛いものですよね。
いつまた電話がかかってくるか、また自
宅に押しかけてくるのじゃないかと、始
終びくびくとしていて、夜も熟睡できません。
もちろん、借りたお金を返さずにいる方
が悪いに決まっています。
しかし、返す意志はありますし、返した
いとも思っています。
でも、それが出来ない状態なのです。
この督促をピタリととめることは、
できないものでしょうか?
それがあるのです!
それは、弁護士や司法書士による
「受任通知」の発送です。
受任通知とは、債務整理を受任した
弁護士や認定司法書士が、
債権者(借入先)へ発送する文書のことを言います。
債権者に送る受任通知には、以下のよう
な項目を書き、債務整理を弁護士などが
受任したことを通知します。
- 債務整理を受任したこと
- 債務者の住所・氏名・生年月日
- 受任した弁護士などの住所・氏名・連絡先
- 債務整理手続きの方針
- 取引履歴開示に関する請求
- 督促の停止
まず、弁護士などが債務整理を受任した
ことを書き、債務整理手続きの方針を説明します。
つまり、任意整理をしたいとか、
自己破産をするなどです。
加えて、取引履歴の開示も請求します。
更には、督促の停止と以後の
連絡は弁護士宛にすることも告げます。
受任通知に書かれている内容は、
「借金問題については、債務者から
当弁護士が受任をいたしました。
以後本人へ直接連絡はせず、
今後は当弁護士まで連絡してください。」
というようなものです。
通常、この通知書は弁護士などが、債務
整理の依頼を受けた直後に発送されます。
早ければ当日、遅くても翌営業日には
発送されるのです。
この受任通知書が届いた時点で、
以後の債務者への直接連絡は完全になくなります。
このように、受任通知は絶大な威力があ
りますが、幾つかの注意点や、
あらかじめしておくこともあります。
- ローンを組んでいる銀行の預金は引き出しておく
- 信用情報機関に登録される
- 連帯保証人への影響を考えておく
- 受任通知が通用しない業者もある
ローンを組んでいる銀行の預金は引き出しておく
のは、口座凍結の場合の対策です。
銀行は、自社のカードローンについて
任意整理が行われた場合、その銀行に
預けている預金は凍結するという措置をとってくるからです
口座を凍結されると、ローン全額を完済
するまでは、その口座のお金は引き出す
ことができなくなります
銀行によっては「ローン残高に充当」
というような措置をとることもあります。
ですから、銀行カードローンを利用して
いる場合は、任意整理前に預金を別の
口座に移しておきましょう。
信用情報機関に登録されるというのは、
いわゆる「ブラックリスト入り」です。
ブラックリストに記載されると、
クレジットカードなどは近々に使えなくなる
可能性が大です。
クレジットカード決済になっている支払
いの変更をしておくべきです。
口座引き落としなどに変えておけばよいでしょう。
連帯保証人への影響を考えておくのは、
保証人へ借金の支払い請求がいく
場合があるからです。
ただし、任意整理では連帯保証人のある
債務は、整理の対象から外す
という手があります。
あらかじめ債務の内容をよく調べておい
て、連帯保証人のある債務は、
整理の対象から外しておきましょう。
受任通知が通用しない業者もある
というのは、いわゆる闇金、特に悪質な
闇金は、受任通知など無視することがあるからです。
そうなると、これはもう警察の出番でしょうね。
受任通知で督促がとまる理由

ではなぜ受任通知によって、取立てが
停止するのでしょうか?
受任通知は、単に弁護士などが依頼人
(債務者)の依頼を受任したというだ
けのものの筈です。
それが督促の停止に繋がるような、
強制力があるものでしょうか?
それがあるのです。
それは貸金業法によるものです。
貸金業法第21条第1項
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の
貸付けの契約に基づく債権の取立てに
ついて貸金業を営む者その他の者から
委託を受けた者は,貸付けの契約に基
づく債権の取立てをするに当たつて,
人を威迫し,又は次に掲げる言動その
他の人の私生活若しくは業務の平穏を
害するような言動をしてはならない。
同第9号
債務者等が,貸付けの契約に基づく債
権に係る債務の処理を弁護士若しくは
弁護士法人若しくは司法書士若しくは
司法書士法人(以下この号において
「弁護士等」という。)に委託し,
又はその処理のため必要な裁判所にお
ける民事事件に関する手続をとり,弁
護士等又は裁判所から書面によりその
旨の通知があつた場合において,正当
な理由がないのに,債務者等に対し,
電話をかけ,電報を送達し,若しくは
ファクシミリ装置を用いて送信し,又
は訪問する方法により,当該債務を弁
済することを要求し,これに対し債務
者等から直接要求しないよう求められ
たにもかかわらず,更にこれらの方法
で当該債務を弁済することを要求すること。
というわけで、受任通知は
法に定められた強制力を持っているのです。
さらには、罰則もあります。
貸金業法47条の3第3号では,上記の第21
条第1項の規定に違反した場合には,
2年以下の懲役、300万円以下の罰金、あるいはその両方の刑罰を科すとあります。
受任通知後の督促は、ムショ送りなのです。
また、業務停止や貸金業登録取消しなど
の行政処分の対象にもなります。
貸金業法以外の法令でも、債権回収会社
による取立て等の業務を制限しています。
債権管理回収業に関する特別措置法(通称サービサー法)18条8項
債権回収会社は,債務者等が特定金銭債
権に係る債務の処理を弁護士又は弁護士
法人に委託し,又はその処理のため必要
な裁判所における民事事件に関する手続
をとった場合において,その旨の通知が
あったときは,正当な理由がないのに,
債務者等に対し,訪問し又は電話をかけ
て,当該債務を弁済することを要求してはならない。
こちらも罰則として、債権回収会社の
許可の取消し等の行政処分があります。
ただし、上記の対象は、貸金業者や債権
回収会社等であり、それ以外の債権者に
ついては、法的な強制力はありません。
債権者が個人の場合などは、該当しないのです。
もう一つ、禁止されるのは、
債務者への直接の取り立てだけです。
裁判による貸金の回収(強制執行)は、
禁止されていません。
悪質な闇金の場合は

前項で悪質な闇金は受任通知も無視する
場合がある、と書きました。
ではそのような業者が、受任通知後に取
り立てをした来たら、どうしたらよいのでしょうか?
まずそのような業者からの電話には出な
いか、録音機能のある電話器なら録音を
取るなどして、警察に届けましょう。
直接押しかけてきた場合は、玄関で相手
を確認したら、決して中には入れず、
すぐ110番に通報します。
結び
借金の取り立ては、弁護士や認定司法書
士に債務整理を依頼し、受任通知を業者
に送付して貰えば、すぐとまります。
債権者に送る受任通知には、債務整理手
続きの方針、取引履歴開示に関する請求、
督促の停止などが書かれています。
この受任通知は、単に債務者の依頼を引
き受けたという意味だけではなく、
法的な強制力もあるのです。
その罰則は、
2年以下の懲役、300万円以下の罰金、あるいはその両方の刑罰なのです。
ただし、任意整理などを自分で行う場合
には、当然この督促停止のメリットはありません。